ニジンスキーと言えば、
20世紀最高とも言われている舞踊家ですが
そのニジンスキーが晩年に観賞に行き激励し
ポーランドの高名な作家で批評家でもあった
ゼレンスキーに、「インドのニジンスキー」と呼ばれた
舞踊家がいました。
ラーム・ゴーパールです。
踊りたくてたまらなかった少年期
ラーム・ゴーパールは
ビルマ(ミャンマー)出身の母と
ラジプト(武士系カースト)で弁護士の父の下に
1912年(もしくは1917年)のバンガロールで生まれ、育ちました。
父は自分と同じように法律家になる事を望みましたが
本人は幼い頃から踊りに惹かれていました。
(この下から挿入していく3つの動画は、
80年代に撮影された一連のインタビューで
上の動画よりもわかりやすい、音楽の入った映像を含みます。
ので、英語が分からない場合も舞踊の部分を狙いながら
飛ばし飛ばし見ていただければと思います)
11歳になる前、家族で泊まったある街の寺院から
信じられないような音量の太鼓の音がしました。
豊穣の感謝祭のための音楽だと聞いて、
その寺院を訪ねると巨大な太鼓が打たれていて
まるで火の上に立っているような
いても立ってもいられない状態になり
上着を脱ぎ捨てると、取り憑かれたように
まさに狂ったように踊り出しました。
そうしなければ足が燃えてしまうように、
心臓から燃え盛るものが手足に伝わっていったのを
はっきりと覚えていて、あれはまさに取り憑かれていたと
そして踊るというのはそういう状態でなければならない、
それが観る者に伝わっていくのだと
上の動画のインタビューでラーム・ゴーパールは語っています。
舞踊と言えば寺院舞踊で、
軽蔑すべきカーストの人間のわざだと
思われていた時代の事。
おそらくそれでも父の了解を得られたのが…
という事かと思われますが
(家出をしたのかどうかは、インターネットで
見つかる限りのソースでは分かりませんでした。
そのうち自伝を入手して読みたいものです)
まだ開校したばかりの、カタカリ舞踊劇の名門学校
ケーララのカラーマンダラムまで行って
カタカリの伝統的な身体訓練を受け
師匠と共に寺院に通うなど
精神性まで含めた修行を経験します。
聖典などもこの時に読んで学び、
「ただ神のように踊るのではなく、
神そのものになる」あり方をこの時に学びます。
マイソールの王宮で踊る機会を得て、
父親は激怒しましたが、
時のマイソール王子に才能を認められて支援を受け、
また王子は両親の説得もしたようです。
世界的に活躍、評価される
その後アメリカ人舞踊家ラ・メリに見出され
世界ツアーに出発した事をきっかけに
(この時に日本にも来て、あわや立ち往生しそうになったりします)
世界的に活躍するようになります。
その後、他のインド古典舞踊
バラタナティヤムやカタックも学びました。
興味深いのは、
カタカリはようやく伝統的な家庭以外にも
教育の門戸を開いたばかりという時期で、
バラタナティヤムとカタックについては、
現在の形式が確立されるまさに過渡期に
ラーム・ゴーパールがこれらの舞踊を
学んでいる事です。
「私の左半身にはバラタナティヤムが、
右半身にはカタカリが、
そして脚にはカタックが宿っている」
と言ったとも言われています。
ラーム・ゴーパールよりも前に
西洋で話題になったインド人の踊り手としては、
ビートルズにシタールを教えた事で有名な
ラヴィ・シャンカールの兄の
ウダイ・シャンカールがいますが(後日記事にまとめます)、
ウダイ・シャンカールが古典舞踊の素養を持たず
のちには古典舞踊家の力を借りながらも
創作の「インド・バレエ」で世界を席巻したのに対し
ラーム・ゴーパールは明確に古典をベースにしていました。
「この世のものとも思われない美しさ」
「この世のものとも思われない身体の制御」
「インドのニジンスキー」
と、西洋の評論家たちは絶賛しました。
古典舞踊をベースとしていたゆえに、
インドツアー中においてさえ、
観衆がその「舞踊言語」
(手話のように、仕草で意味を伝える)
を理解せず、それゆえに楽しみきれていない事に気がつくと
内容が伝わりやすいように
演目をアレンジするようになりました。
また、衣装も伝統的な細密画や彫刻などを研究し
特別に制作しました。
ラーム・ゴーパールの舞踊の中には
カタカリの舞踊を、カタカリのあの化粧や
装束なしに、独自の衣装で行なっているものもあります。
更に、マハトマ・ガンディーの勧めで
舞踊の演目の前にその内容の説明をするように
なったと言います。
このやり方はインドで好評・成功を収めたので
西洋でも応用されました。
…ひょっとして、この「内容を説明する」
という、今では割と一般的な形式は、
この辺りから始まっているのかしら
と、思ったりします。
また、現在に繋がるインド知識階級への
一種の「芸術教育」の鏑矢となったのでは、とも。
イギリスでの晩年
ラーム・ゴーパールは生まれ育ったバンガロールと
イギリスに舞踊学校を開きますが
どちらも長続きはしなかったようです。
卓越した芸術家であり
多くのパトロンに愛されたラーム・ゴーパールでしたが
マネージメントには弱く、また良いマネージャーには恵まれなかったのかもしれません。
2003年に亡くなるまでの30年を南ロンドンで過ごし、
生活はフランスのパトロンや、ロイヤル・オペラ・ハウス、
クロイドン・カウンセルなどの援助を受けました。
晩年は南ロンドンの介護ホームで、
少数の支援者に世話されていました。
1990年にはインドの功績ある芸術家に贈られる
Sangeet Natak Akademi Fellowshipを、
1999年には大英帝国勲章を授与されています。
しかしこの時には既に80歳前後、舞踊家の盛りをとうに過ぎていました。
現在ラーム・ゴーパールの名が忘れられかけているのは、
彼の名を語り継ぐ弟子などの継承者がいないからでしょう。
私がラーム・ゴーパールに惹かれるのは、
(彼の舞踊そのものを語る事は、
少ない映像記録や時代性の装飾から
語りにくい部分があるのですが)
何となくの彼の佇まいや語り口…という事もありますが
自身は様々な見せ方をしつつも、
あくまで古典舞踊に留まりながら
たとえばウダイ・シャンカルなどの
より自由に創造性を駆使した先駆者、
そしてヨーロッパの古典舞踊家たちに
ごくごく自然で純粋な敬意を持ち続けたらしい事があります。
彼から滲み出るある種の純粋さに
私は自ずから惹きつけられるように思われます。
とても正直なところを吐露してしまえば、
いわゆるハーフであるところ、
母親がビルマ(ミャンマー)人であるところも
ご本人はあまり言及していないようですが、
私が肩入れしてしまう一因かもしれません。
ついでに言えば、彼の舞踊や精神性のベースが
ケーララで形成されている事も、
ケーララに深く親しみを持つ私にとっては
勝手な親近感を感じてしまう要因です。
(全く本筋からは逸れますが、
イギリス帝政下のインドでは、
割と「見た目が違う」事は当たり前だったのかしら…
と気になるところがあります。
タゴールの小説「ゴーラ」でも、
主人公が最後に「自分は実は白人の子どもで、
インド人バラモン夫婦の養子になっていた」という事を知ります)
後継者の不在と、
古典舞踊とも創作舞踊とも括りがたい存在であるが故に
インド舞踊史に中々名前の出て来ないラーム・ゴーパールですが
一人の舞踊家として非常に魅力的な存在だと
ここで微力ながらご紹介できればと思いました。
参照:(Last Retrieved 20th February 2020)
https://www.asianage.com/life/art/211118/remembering-ram-gopal-who-put-indian-dance-on-the-world-map.html
https://www.sahapedia.org/ram-Gopal-1912–2003
https://www.theguardian.com/news/2003/oct/13/guardianobituaries.india








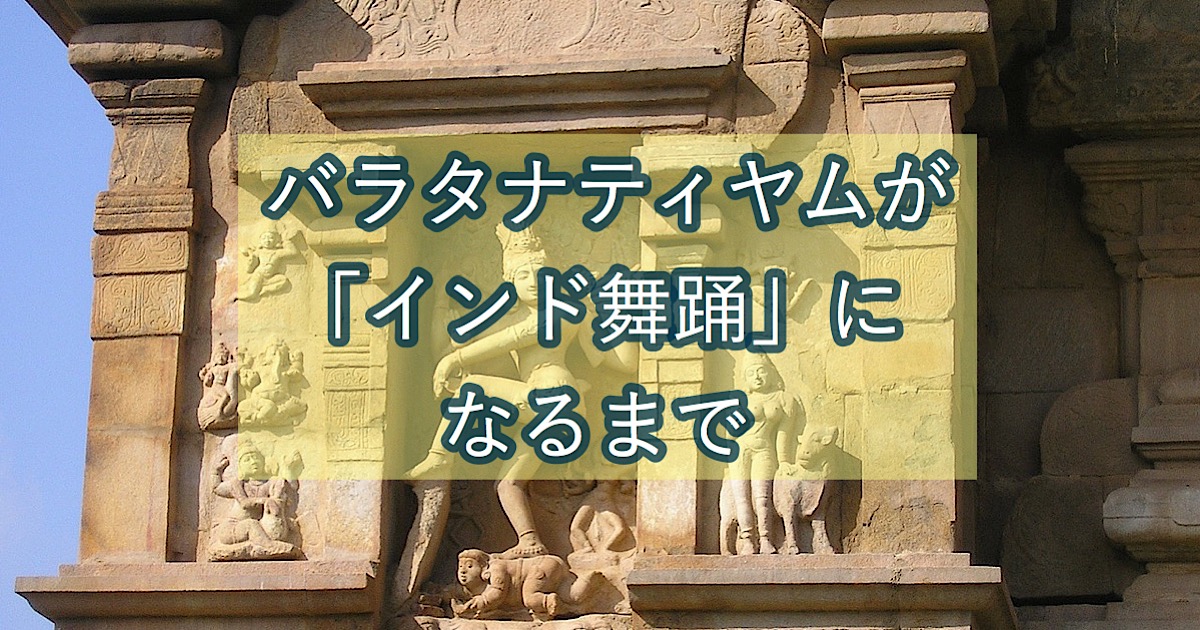



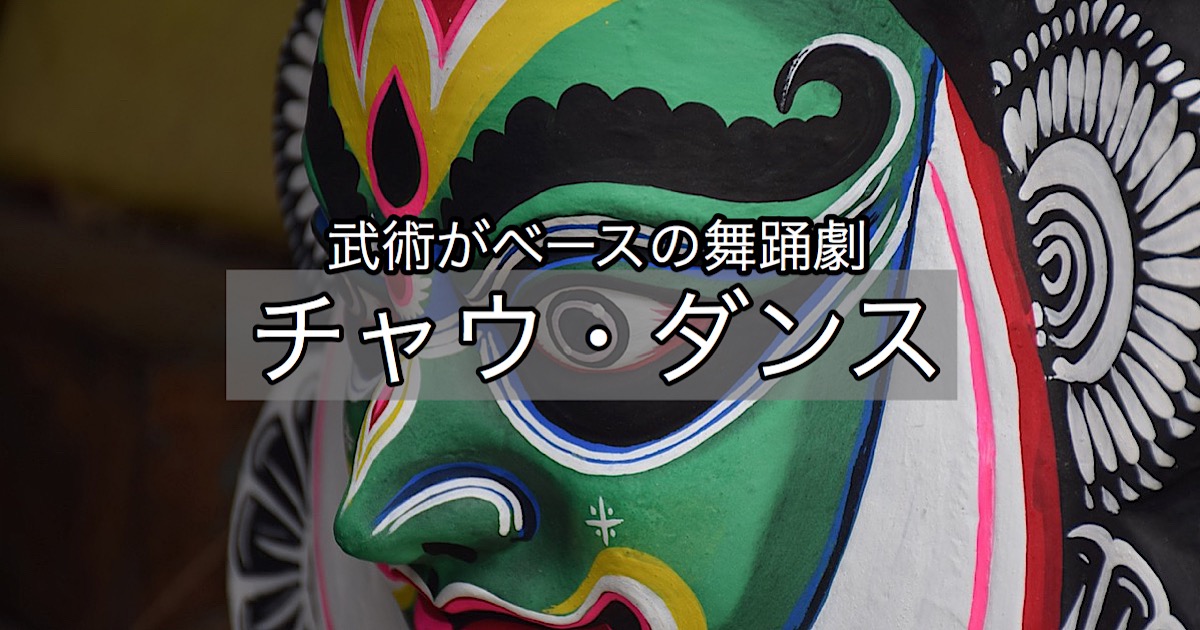








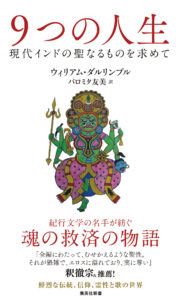











コメントを残す