なぜ呼びかけるのか
そういえば、保育園に 伺ったときにした話で バウルの公演では最初に 聖者やグル、神さまに呼びかけて、 ここに来てください 私の心の蓮にいらしてください とうたうことが多いです。 バウルにとっての神さまは お空の向こうにお…
 ヨーガ
ヨーガそういえば、保育園に 伺ったときにした話で バウルの公演では最初に 聖者やグル、神さまに呼びかけて、 ここに来てください 私の心の蓮にいらしてください とうたうことが多いです。 バウルにとっての神さまは お空の向こうにお…
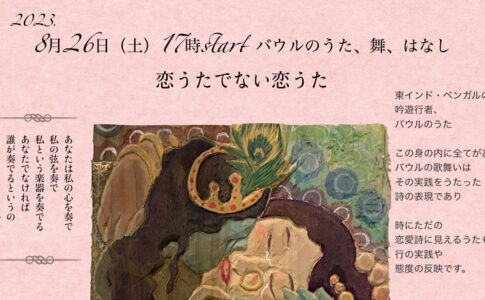 スケジュール
スケジュール特に、私自身のうたを 人前でうたうようになってから 顕著なのですが、 「恋唄に聞こえる」うたがある (もちろん間違いではない) ということで 元々、私からすれば 「敢えて言うなら信仰の歌だと 受け取られるんじゃないかな」…
 スケジュール
スケジュール「歌い手はやがて消え、うただけがある」 と師匠ひいてはバウルは言います。 そのうたは先師たちの言葉、 うたうことで先師が顕現する。 そのために本来の声という、 透明な状態が要る。 その先師も更に先師を体験した。 そうやっ…
 スケジュール
スケジュール日本語のうたが できるようになって、 ベンガル語でうたう という体験も変わってきた、 という話は、 何度かあちこちで してきたのですが 最近は、また一周?半周?回って ベンガル語の方が、 語るように歌えるように なってき…
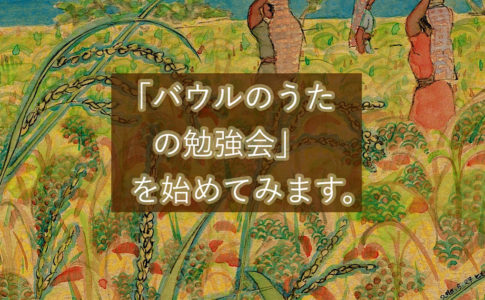 スケジュール
スケジュールバウルのうたの勉強会 【予約:https://baulsongjp.peatix.com/】 というのを始めることにしました。 原則として第4金曜日19-21時(パロミタが日本にいるときの)に行います。 勉強会、としてい…
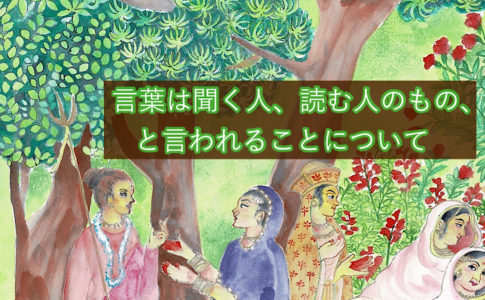 文化
文化言葉は聞く人や読む人のもの、 と言われることについて というのはつまり、 一度作者の手を離れた作品は それを受け取る人のもの どのように受け取られても、 それはその受け取る人のもの ……ということで、 それはその通りだと…
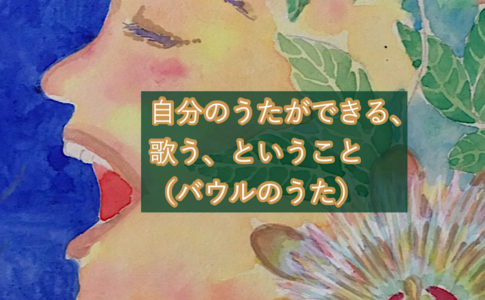 パロミタのこと
パロミタのことある晩、何だか動けなくなって寝っ転がっていたら、急にうたが降りてきたということがありました。 ここ数年、「自分のバウルの、日本語のうたが作れるようになるのは一生の野望」的なことを言ったり、 「次のソロ公演の前にはまずは日…
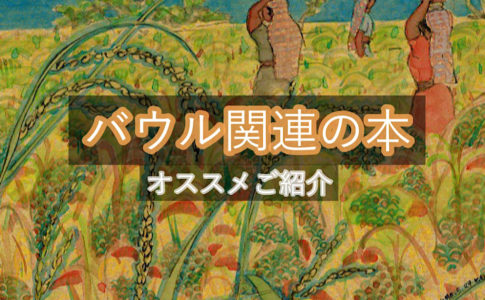 ヨーガ
ヨーガ以前から書くと言って書かずじまいだった、バウルについて日本語で書かれた本のご紹介です。実はけっこうあります。 少し名前が出てくるだけ、とかだともっとありますがここでは比較的手に入りやすくまたひとりの実践者である私から見て…
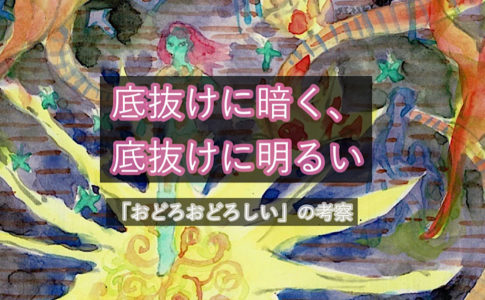 ヨーガ
ヨーガ「おどろおどろしい」「妖しさ」という言葉を、先日の公演の感想で見かけて、驚いたと言うのも変ですが、意外でした。 マーダヴァ、どうか私の、内なる扉へおいでくださいマーダヴァこのいのちの友 あなたの笛の音をどうか甘やかにずっ…
 ヨーガ
ヨーガ行者は怒りもや悲しみも 人にぶつけず、 すべて「あの方」に捧げる。 よろこびも、悲しみも、 すべての感情を。 これはかなり初期に 師匠に言われた言葉で、 深く印象に残っているものです。 また別の時には、 どんなことも、 …