私はケーララに住んでいた頃、彼の主催する音楽祭に通っていました。
共演者や招待アーティストが大好きで仕方ないという風に語り、
すごく楽しそうに歌う彼の、すっかりファンになっていました。
王族に生まれながら、その枠に収まりきらず、
意欲的に南インド古典音楽界、そして王家に改革を起こしていくラーマ・ヴァルマさん。
来日公演では通訳をさせていただいて、とても嬉しかったです。
2記事続けてご紹介しますの後編。長い方、本命の記事です。
元記事:[https://www.thehindu.com/entertainment/music/music-gave-me-a-sense-of-purpose-says-rama-varma/article26331174.ece]
王宮に育ち古典音楽家になったラーマ・ヴァルマは50歳になり、これまでの道のりを振り返る。
伝説的な歌手で作曲家でもあったバーラムラリクリシュナの一番弟子と言っても過言ではないであろう、アスワティ・ティルナール・ラーマ・ヴァルマは声楽家でありヴィーナー奏者、そしてかのトラバンコー王家マハラジャ音楽家・スワーティティルナールの直系の子孫である。運命の王子と言ってもいい。「壁を壊し、絆を結ぶ」というタイトルはまるで政治的な公約のキャッチフレーズのようだが、なるほどふさわしいと言えよう。このエッセイ集は彼の50歳の誕生日を記念して作られ、ラーマ・ヴァルマの人格と音楽に通底する公平なまなざし——スワーティ・ティルナールから受け継いだ——へのトリビュートでもある。
最初のエッセイでは、彼が故マンナ・デイ(ベンガル出身の高名な歌手・音楽監督)を訪れた際にベンガルの詩聖タゴールの詩を歌ったというエピソードが紹介されている。その夜、停電が起きた時に、「Amir ei dehokhani tule dharo tomar oi debaloye pradip karo (私の身体を灯にして、あなたの神の家を照らして下さい)」とベンガル語で歌い出して周囲を驚かせたというのだ。
また、ある時楽聖ティヤーガラージャによる ラーガ・リーティガオラの曲「Paripalaya Paripalaya Paripalaya Raghunatha」を教えていたレッスンで、ほとんど同じ意味のあるタゴール・ソングに言及したという。
その人当たりがよい柔らかな物腰はラーマ・ヴァルマの変革への希求を巧妙に覆い隠すが、歴史に学ぶ謙虚な姿勢も併せ持っている人である。ある暖かな日曜の昼下がり、昼食を共にしながら話を伺った。話を通して明らかになったのは、彼のなしえた王室による芸術保護の改革は、彼の個人的な変遷と切り離せないものであるという事だ。
幼い頃、実家であるトリバンドラムのカウディアール宮殿にはいつも高名なカルナーティック音楽家達が訪れ、音楽に溢れていた。ラーマ・ヴァルマの曽祖母、アンマ・マハーラーニー・セートゥ・パールワティー・バーイーは音楽を呼吸するように生きた人で、トリバンドラムじゅうの音楽家と面接した後に曽孫の師としてヴェチュール・ハリハラスブラマニア・アイヤールを選んだ。その後声楽の授業が進んでいくと、同時にヴィーナー(弦楽器)もK・S・ナーラーヤナスワーミーから学ぶようになった。
1980年代中頃、若き王族が音楽の道を選ぶという事は考えられない選択だった。何世紀にも渡って芸術のパトロンであったが故に、自分達の中から音楽家を輩出するという事は、全く想像もつかない事だったに違いない。「音楽が僕に人生の目的と、進むべき道を導いてくれた」こう語るラーマ・ヴァルマの声には真摯さがある。そこに彼の尽きる事ないエネルギーの源泉があるのかもしれない——知られざる曲を発掘し、国内外を精力的に飛び回り、数十年に渡って続けて来たワークショップで教えた生徒は何百人もいる。
ラーマ・ヴァルマがステージで公演できるようになるには、T.V.ゴーパーラクリシュナンによる度重なる説得を要した。マルチな才能を持つこのベテラン音楽家が、この若者の豊かな才能を認め、育てるべきだと王家の面々に掛け合ったのだ。興味深い事に、彼の初公演は1990年のメー・デーに行われた。彼がやがてカルナーティック音楽界にもたらす数々の改革を、何か予感させるような日取りである。女神ドゥルガーを祭るナヴァラートリ・ドゥルガー・プージャーの祭礼では毎年9日間に渡り音楽家を招いて公演が行われるが、数世紀に渡り女性の登壇は許されていなかった——この状況を変えたのはラーマ・ヴァルマである。また、その際の音楽家達への謝礼がその技量と知名度に見合ったものになったのも、ラーマ・ヴァルマの功績である。
5月1日のトリバンドラムでの初公演は、ムリダンガムにT.V.ゴーパーラクリシュナン、バイオリンにV.V.スブラマニヤムという伴奏者を迎えて行われた。それから1991年、アメリカでひと月に20ほどものコンサートをしてからというもの、もう振り返る事は無かった。
ラーマ・ヴァルマの声楽の妙技が聴衆をとりこにする一方、 曲ごとの分かりやすい解説は彼らの知性や歴史への好奇心を刺激する。たとえばラーマ・ヴァルマは伝説的な宮廷音楽家イライヤーマン・タンピの曲「Karunacheyvan endu」について、歴史的な事実が明らかにされるべきだ、と言う。現在よく知られた旋律がチェンバイ・ヴァイディヤナータ・バガワタルによってヤドゥクラカンボージ・ラーガの旋律を付けられたものであり、元々はシュリー・ラーガで作曲されていた事を知る人は、音楽愛好家の中でもほんの一握りである。こうした現象は、同じくタンピ作曲の子守唄にまつわる近年の騒動に関連しても一考に値するだろう。{映画「ライフ・オブ・パイ」のアカデミー賞候補にもなった挿入歌がタンピによるよく知られた子守唄の剽窃だと批判された*訳者注}
また、ティーガラージャの有名な「Endaro Mahanubhavulu」では、”Kamalabhava sukhamu sadanubhavulugaka’’という詩の意味は「梵ブラフマンのよろこびを常に体験する人」である、と解説する。また、バーゲーシュリー・ラーガの曲 ‘Sagara sayana vibho’では、 M.D. ラーマナータンはヴィシュヌ神を「シュリー女神とブーミ女神と共に威風堂々と立っている」と表現するが、この歌詞は‘Baga Shri Bhoomi Sahithudai Velayu,’ で、ラーガの名前であるバーゲーシュリーの音に聞こえるような言葉選びをしている事が分かる。このような語りでいっそう充実するラーマ・ヴァルマのリサイタルは、音楽が女神ドゥルガーへの捧げ物であるナヴァラートリ・ドゥルガー・プージャーでも目玉となっている。
このように教育と美意識、そしてエンターテインメントを統合しようという強い意識は、十代の頃熱心に収集した西洋古典音楽のアルバムの詳細なライナーノーツに影響されたものだという。知識をシェアする事は、伝説的な作曲家や音楽家達に敬意を表する手段であり、また義務であるとラーマ・ヴァルマは言う。
ヴィーナー奏者という肩書きもお飾りの名称ではない。「楽器の演奏を知らない歌手は、たとえば英語を喋れても書けない人のようなものだ」。その効果は、近視の人が眼鏡をかけた時にも似ている。楽器演奏を学ぶ事は、旋律の中の細かい音符の動きを把握する能力を高め、鋭くする。これができないと、何年もしてからそうした曲の繊細さでつまづいてしまうかもしれない。
往年の名歌手、M.S.スッブラクシュミ、M.バーラムラリクリシュナ、チェンバイ・ヴァイディヤナータ・バガワタルや M.D. ラーマナータンらも何らかの楽器演奏に熟達していた。現在活躍中のベテランでも、T.V.ゴーパーラクリシュナン、ネイヴェーリ・サンタナゴーパーラン、T.N.シェーシャゴーパーラン、S.ソウミヤらも楽器演奏に精通している。伴奏者たちは歌手が楽器演奏に通じているかすぐに分かるし、逆もまた然りだとラーマ・ヴァルマは言う。
亡くなるまで15年間師事したバーラムラリクリシュナとの特別な絆について、ラーマ・ヴァルマは謙遜してあまり語ろうとしない。師自身が「バーラムラリクリシュナはラーマ・ ヴァルマからバーラムラリクリシュナについて学んだ」とうそぶいたと言うが、ラーマ・ヴァルマは穏やかにその存在の偉大さについて本人に気づかせていったのだろう。そうした思い出はラーマ・ヴァルマの中で永遠に生き続ける。
エッセイ集「壁を壊し、絆を結ぶ」の中で詩人シュリークマール・ヴァルマによるトリビュートがまた心を揺さぶられる。「もしいつか、ラーマ・ヴァルマが音楽の神として祭り上げられ、象徴として祀られるようになったら、その時はけして、彼が気分屋などではない天才だとは、偉そうではない改革者だとは、誰にも言わせないように。誰も彼のいたずら好きな魅力を無視しないように、彼が音楽家であると同時に読書家であったと忘れないように。その博識を生かしたのは常に彼の入念な稽古だった。グルメである事が影に追いやられないように、世界の音楽への尽きない興味が、カルナーティック音楽への貢献に無視される事が無いように。…彼の内に共存する不遜さと深い精神性を、いつも忘れる事が無いように。」




















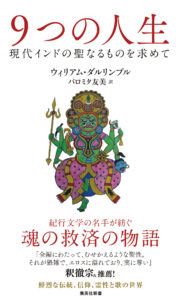












コメントを残す