大学時代のサンスクリット講座のグループページに
マッコーマス教授が投稿された内容がとても素敵なので、
こちらで翻訳紹介いたします。
英語の元記事をここに埋め込もうと思ったのですが、
招待制グループの記事だからかできないので、
気になる方はこちらから直接ご覧ください……
あれ、見られないのかな?
シェアする許可はいただいております。
– – –
サンスクリット語学生3年目、アデレードからご参加のラージャー・フイルゴール教授はインド分離独立前の南インドのお生まれです。最近の授業で、子どもの頃、お祖母様に一年に一日だけ、食べ物を物乞いをするようにと外に出されたことを話してくださいました。慈悲と謙虚さを学ぶためだったそうです。そのお話と、当時の教授のかわいらしいお写真がこちらです。皆さんもどうぞ楽しんでいただけますように。
—
シュラーヴァナ月の最初の月曜日は、年に一度の物乞いの日で、いつもよりも早く起きなければ行けませんでした。学校(小学校でも中高でも)に間に合うように、地域を回るためです。
祖母は、私が物乞いになる可能性もある。すべてはデーヴェーッチェー(カンナダ語で「神の思し召し次第」)だ、と言ったものでした。器はふたつ持って行きました。ひとつはお米用、ひとつは豆用です。家の玄関の前に立って大きな声で「bhavati bhikṣāndehi mātā annapūrṇeśvarī(どうか喜捨をください、母なる[食物を司どる]アンナプールナ女神)」と唱えると、すぐに反応する家もあれば、そうでない家もありました。「最近は物乞いが多すぎる。今度の新しいのは誰?」という女性の声などが聞こえて来ました。私がずっと同じ言葉を繰り返し続けるので、子どもが様子を見にやられて来ました。そうするとその子は走って戻って、「男の子がいるよ」と伝えます。その時になって、女性(この子どもの母親か祖母)が出てきて、私がアナンタアーチャールの孫だと分かってお米か豆をくれました。私が家に持ち帰った食べ物は、お手伝いの人たちにあげて、彼らが料理して食べました。
この体験は、物乞いの身になって心を寄せることを教えてくれました。今でもそうです。今でも祖母の言葉を覚えています。「物乞いに失礼な態度を取ってはいけないよ。既に充分苦しんでいるんだから」
サンスクリット語を学ぶのはとても面白いです。子どもの頃にやりたかったことで、高校ではサンスクリット語の授業もあったのですが、私は既にカンナダ語と英語、ヒンディー語という3つの言語を履修していて、時間割に組み込むことができなかったのです。インドが独立したのは私が高校に入って2ヶ月後の1947年6月のことで、祖父は私にヒンディー語を学ぶことを勧めました。先見の明があったと言うべきで、私はその後ベナレスの大学に進んで機械工学の学位を得ることになります。




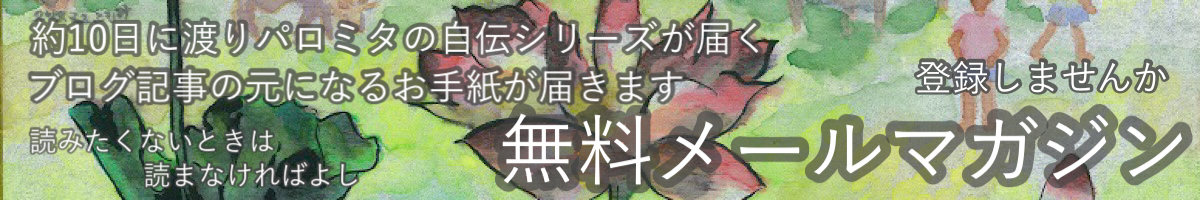



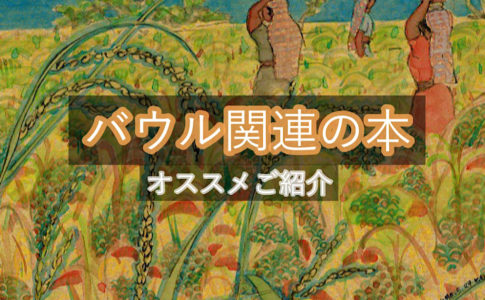
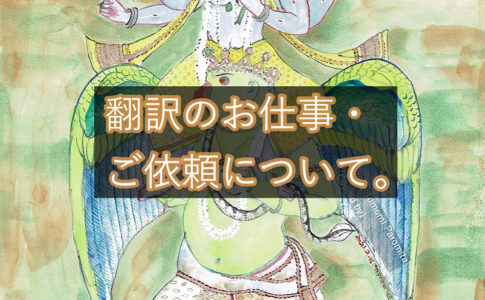

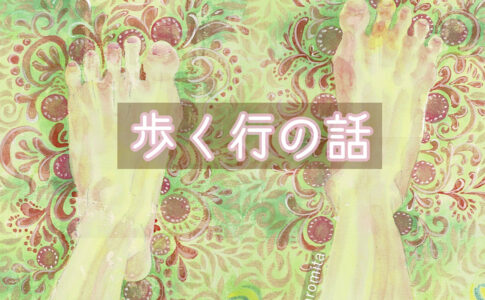



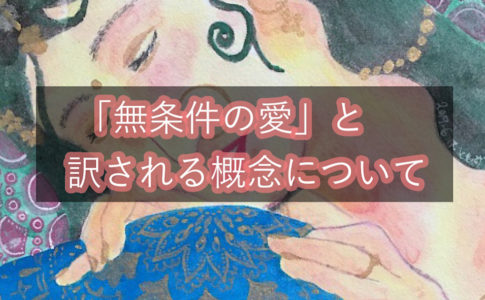


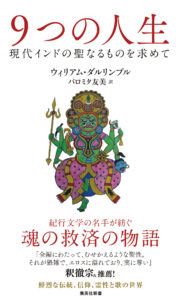
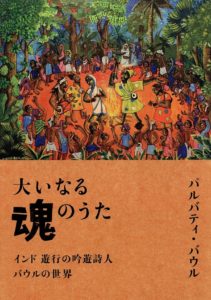


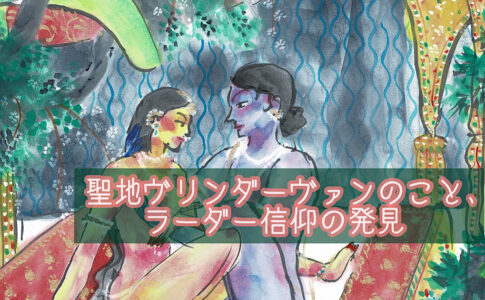



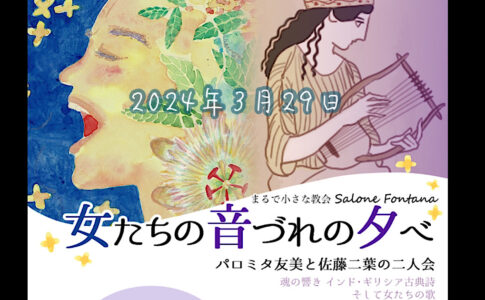

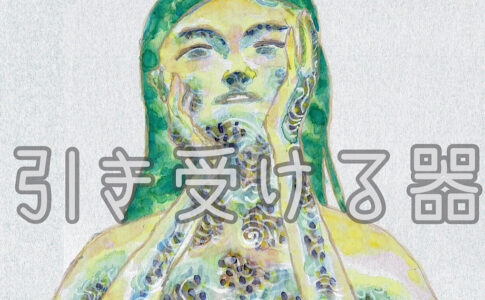

コメントを残す