あるグルが「厳しい」と
形容される時、
その厳しさとは何だろう。
ということが、かなり何年も
ずっと疑問でした。
日本でもよくある話ですよね、
厳しさの名の下に行われる
暴力や抑圧、弱者への八つ当たり。
それでは、そうではない
「厳しさ」とは何なのか。
厳しさとは何か、というのはかなり何年も疑問だった。心底納得できるようになって初めて弟子になれたように思うし、学び自体変質した。それまでの過程は割と苦しみが主体だったけどそれでも選び続けたことそれ自体が答えとも言えるかも。普通は、納得できないなら離れた方がいいです。
— パロミタ (@Tomomi_Paromita) March 25, 2021
修行する人とそれ以外の人は前提が違うという考えで、私の語るのは基本、修行者の話です。それが光岡先生のおっしゃるガチスピという事にも繋がるのかと思う(フォロワー10人増えたので確認しに行った笑)。修行者は修行しない人に優しくすべきみたいな価値観があるのですが、どこから身につけたのか不明
— パロミタ (@Tomomi_Paromita) March 25, 2021
修行者は苦しみや辛さも贈り物として受け入れる(私にそれができているとは言いません)。抑圧だとしてもそこにただ己を見る。でもそれはやっぱり、ただ個人である普通の人(ちゃんとした師がいなく修行をしていない)には危険だと思う。師匠になるのも全く遊びではないというのはそういうところもある。
— パロミタ (@Tomomi_Paromita) March 25, 2021
厳しさという概念、アイデア、コンセプト。
厳しさというもの自体
現代人には扱いがたい、
理解しがたいものなのだと
今は思います。
今は、誰しもが平等で
先生と生徒も
対等に、友人のように
接することがスタンダードというか
求められている時代
と言えるでしょう。
厳しさは、誰かが
誰かよりも、絶対的に
知識や、能力や、賢さや
何かしらにおいて
他の誰かよりも優れていて
その人の判断において
他者に対してなすことを
正しいと前提する
そうした土壌において機能する、
成立する、花開けるものです。
誰もが全てにおいて対等である
という前提では
「今は理解できなくても
この人がなすことは意味がある」
という留保や信頼が機能せず
誰しも誰にでも批判ができるし
その環境では、より
その反動としての
依存やカルト化に脆弱になる
ようにも思われます。
(これは単なる私の仮定で、
想像なので、信じないでください)
まあ、根本的には
確かに皆、対等であり
それはそれとして
普遍なのだと思いますし
少なくとも現代において
実際、その厳しさを
信頼するに値するだけの人は
絶対数として少ない
という気はします。
私自身、ご本人は
厳しさとお思いのようだけど
仮にただの気分屋でないにしても
教育方法として、ひどく
効率が悪く、ただ
生徒の自尊心を傷つけ
心を弱らせるだけのことをしているな…
と思われる場面を
見たこともあります。
「厳しい」教育を受けたからこそ
他人にも「厳しさ」を求める場合もあれば
反動で、そういった全てを
否定するような場合もある。
そうした状況などを見ながら
厳しさとは何なのか、を
かつて考え続けていました。
考え続けると、
なんというか飽和してしまって
特に考えることが無くなる
ということが、たまにあるのですが
これもそんな具合で、
今日はとても久しぶりに
思い返して書いています。
私の場合は、師弟関係にあり
バウルのうたを歌っているうちに
何というか、納得して
腑に落ちてしまったところが
あるんですよね。
バウルは、あと多分、
ほとんどのインドの伝統は、
グル・ヨーガなしには
成り立ちえません。
人は基本的に驕るし、道を誤る。生身の師(ほんものの)がいれば雷を落とすところ、いなければ現実が牙を剥き痛みつける。そこに濁らず透明に学びを読み取るのもただ個人ではまあ、大変だ。現代の日本はそういう意味では、とてもつらいよね、と思う、まあ現代社会はどこもそうですが。
— パロミタ (@Tomomi_Paromita) March 25, 2021
やはり厳しさとは
いわゆる、本当の「愛」というものが無いと
そもそも成立しないもので
その「本当の愛」が中々分からない
迷走する時代においては
「厳しさ」が成立しにくくて、
当たり前なのでしょう。
また、たとえば
「所詮は人間のやること」
という言葉があって、
それ自体はおそらく
ただの事実で、真理でもある
のかと思いますが、
その、人間を
必要以上に低く見積もる心性に
今の私は同調できません。
少し前なら、
同調していたと思いますが
今は、同調するには、
普通に凄い人を見すぎました。
こうした認識も、
厳しさのあり方には
関わってくるように
思われます。




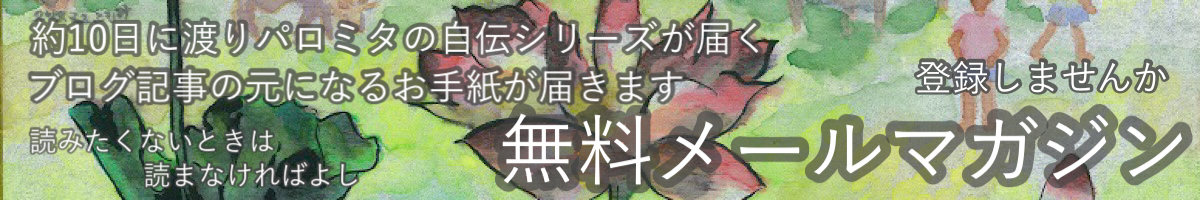
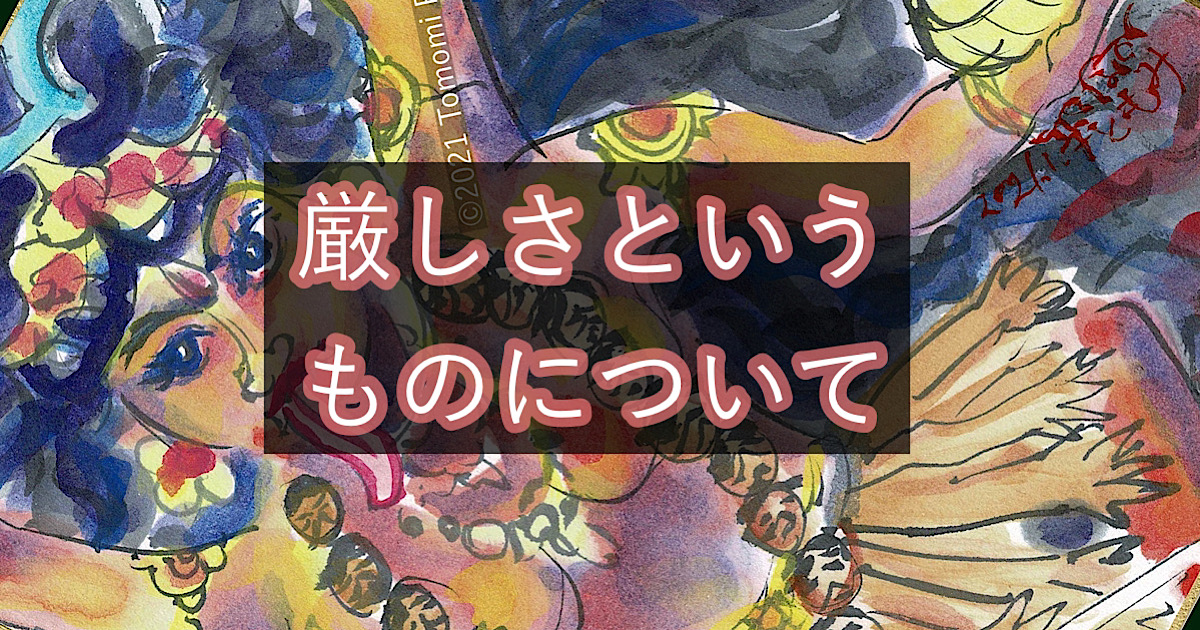
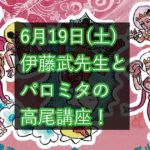

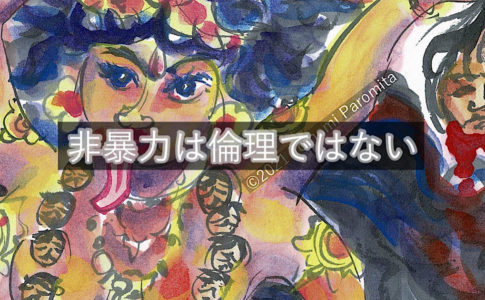
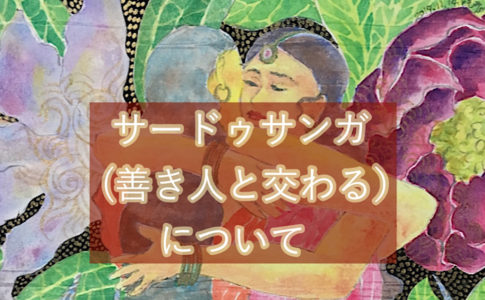
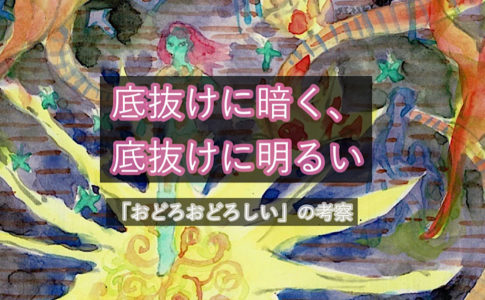
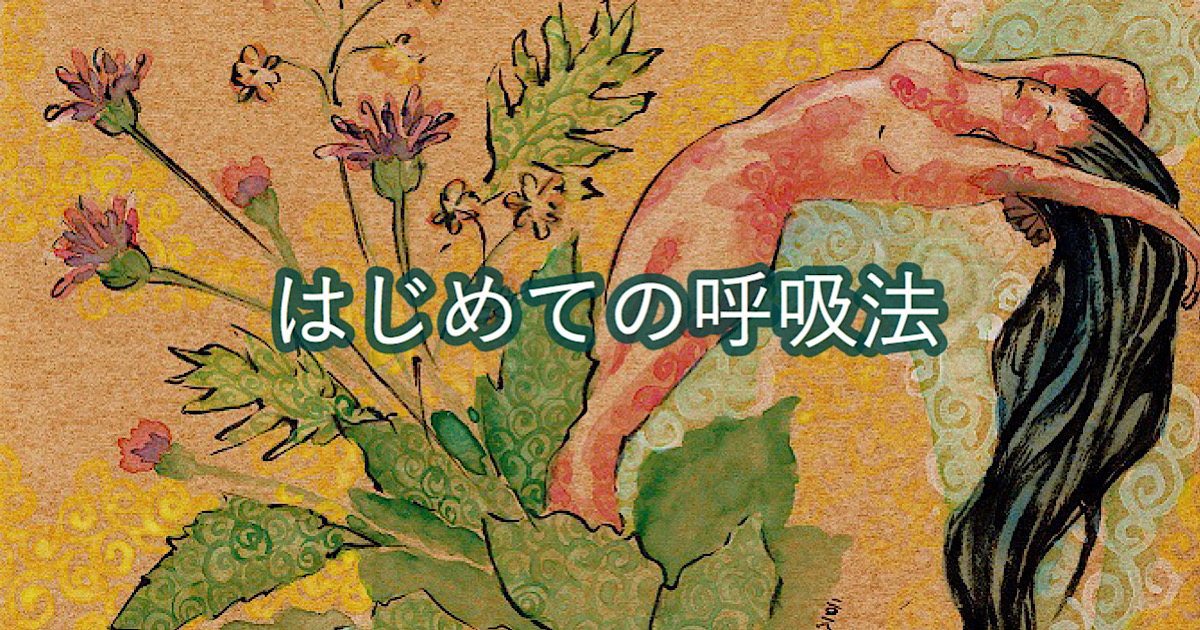


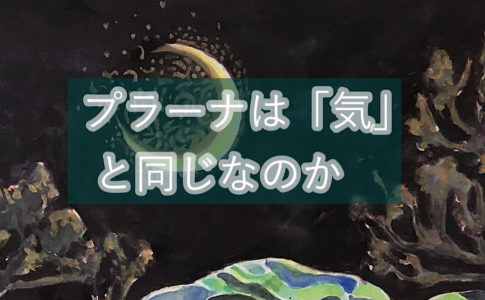
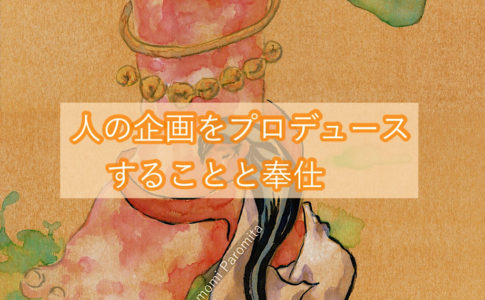


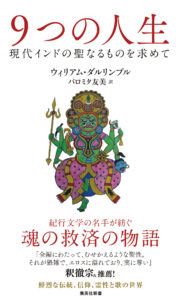
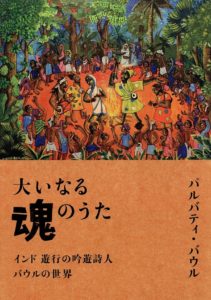


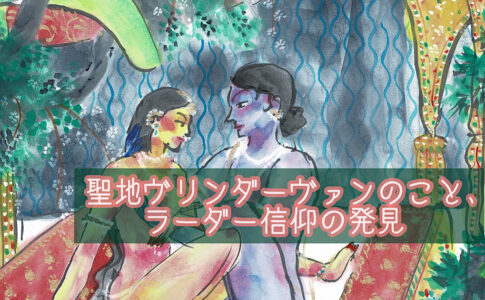



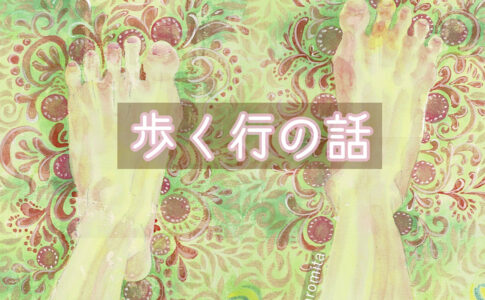
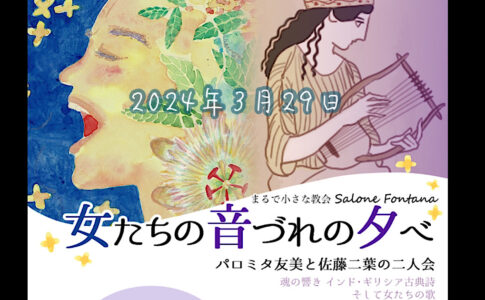

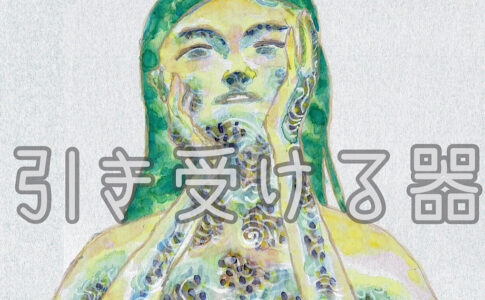

コメントを残す